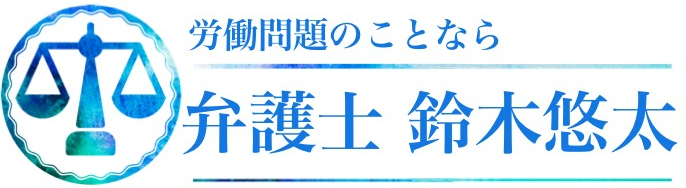【解雇事件マニュアル】Q85 懲戒解雇の理由を後から追加することはできるか
1 懲戒解雇の意思表示時点で存在していた事由の追加
使用者が、労働者に懲戒解雇を通告した際には主張していなかった事由を、解雇訴訟等において後から解雇理由に追加して主張することがある。このような解雇理由の事後的な追加は許されるのか。
⑴ 使用者が懲戒解雇の意思表示時点で認識していなかった事由の追加
普通解雇の場合には、解雇時に使用者が認識していたか否かにかかわらず、解雇の意思表示の時点で客観的に存在していた事由であれば、後から解雇理由に追加して主張しても、それだけで失当とはならないというのが実務上の扱いである。
これに対して、懲戒解雇の場合には、懲戒解雇当時に使用者が認識していなかった非違行為は、特段の事情がない限り、その懲戒の理由とされたものではないことが明らかであるから、その存在をもってその懲戒の有効性を根拠づけることはできないとするのが判例である(山口観光事件・最一小判平8.9.26労判708号31頁)。
したがって、使用者側が懲戒解雇当時認識していなかった非違行為を懲戒解雇の懲戒事由として主張しても主張自体失当となる(『類型別Ⅱ』389頁)。
「特段の事情」とは、懲戒解雇とされた非違行為と密接に関連した同種の非違行為の場合などを指すとされており(菅野ら『労働法』670頁)、『類型別Ⅱ』389頁は、具体例として、一連の横領行為の一部のみの調査が先行し、これのみで労働者を懲戒解雇したが、その後の調査でその前後の横領行為が判明した場合を挙げている。この例の場合には、調査中である前後の横領行為についても懲戒の対象となることが労働者にとっても明らかであるといえるだろう。
⑵ 使用者が懲戒解雇の意思表示時点で認識していた事由の追加
菅野ら『労働法』670頁は、「認識していなかった非違行為」とは、「理由として表示しなかった非違行為」というべきであるとして、懲戒解雇時に使用者が認識していたが懲戒解雇の理由としなかった事由についても、懲戒解雇時に使用者が認識していなかった事由と同様に、「特段の事情」がない限り、後からこれを懲戒解雇の理由に追加することは許されないとしている(水町『詳解労働法』599頁も同旨)。
もっとも、富士見交通事件・東京高判平13.9.12労判816号11頁は、懲戒当時に使用者が認識していなかった非違行為については「特段の事情」がない限り、その存在をもって当該懲戒の有効性を根拠付けることはできないとしつつ、「懲戒当時に使用者が認識していた非違行為については,それが,たとえ懲戒解雇の際に告知されなかったとしても,告知された非違行為と実質的に同一性を有し,あるいは同種若しくは同じ類型に属すると認められるもの又は密接な関連性を有するものである場合には,それをもって当該懲戒の有効性を根拠付けることができると解するのが相当である。」とし、「特段の事情」までは不要として比較的緩やかに懲戒理由の追加主張を認めている。群馬大学事件・前橋地判平29.10.4労判1175号71頁は、より明確に、懲戒当時に使用者が認識していなかった非違行為と、懲戒当時に使用者が認識していた非違行為を区別している。
しかし、罪刑法定主義類似の諸原則が適用される制裁罰である懲戒解雇について、処分時に明示されていなかった理由を事後的に追加することを安易に許容することは、適正手続きの観点から妥当でない。
また、仮に使用者が懲戒解雇当時に認識していたにもかかわらず、当初懲戒解雇理由として主張していなかった事由については、使用者は当該事由を懲戒解雇に相当するものとして重要視していなかったというべきである。
したがって、使用者が懲戒解雇の意思表示時点で認識していたにもかかわらず、事後的に追加した懲戒解雇理由が、決定的に懲戒解雇の有効性を基礎付けることはないというべきであろう。
2 懲戒解雇の意思表示時点で存在していなかった事由の追加
懲戒解雇の意思表示時点で客観的に存在しておらず、懲戒解雇後に新たに発生した事由は、既にされた懲戒解雇の理由にはなり得ず、使用者が後から懲戒解雇理由に追加して主張しても、当該主張は失当である。
もっとも、新たな事由が発生した後に、使用者が労働者に対して新たな懲戒解雇(ないし普通解雇)の意思表示をすることはできる。当該解雇は、既にされている懲戒解雇が無効だとしても新たな解雇により雇用契約が終了しているという意味で予備的解雇に位置づけられる。